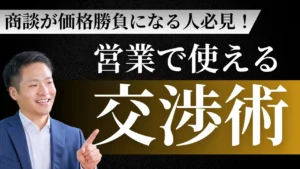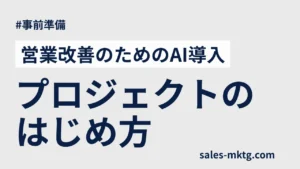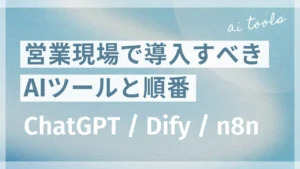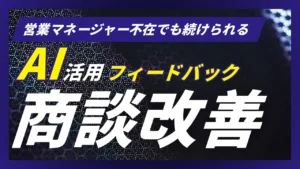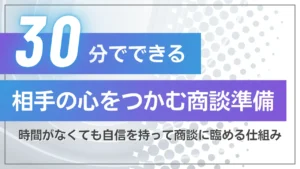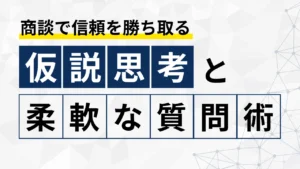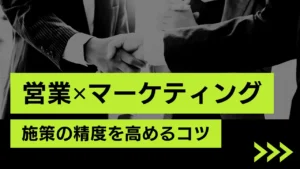営業の現場では「事例資料」を持っていても、いざ商談となると十分に活かせていないことが多いものです。
特に「数値的なビフォーアフター」だけを並べた事例集は、聞き手にとっては表面的な情報に映り、会話が広がりにくい…。そんな経験はありませんか?
 営業マネージャー
営業マネージャー実績紹介をしても“他社は他社”で片付けられてしまうんです。
数字の成果だけ伝えても、なかなか自分ごととして受け止めてもらえなくて…。



確かに数字だけでは“へえ”で終わってしまいますね。
大事なのは、成果が生まれた背景やプロセスまでを社内で整理しておくことです。直接見せる必要はなくても、それをもとに営業が対話を組み立てれば、商談を自然に前進させることができます。
つまり、事例シートとは「顧客に配るパンフレット」ではなく、営業がシナリオを描くための社内資産です。
表面的な実績紹介ではなく、背景情報を蓄積し再利用できる形にすることで、属人化を防ぎ、チーム全体の商談力を底上げできるのです。
- 数値的なビフォーアフターだけに頼らない「事例シート」の考え方
- 社内資産としての事例整理と、商談に活かすための具体的ポイント
- 再現性あるフォーマットと実践例
イントロダクション:なぜ事例シートが必要なのか
事例シートとは何か
「事例シート」とは、商談を前進させるために事例を“再利用可能な形”に整理した社内用のシートです。
特徴は「顧客に直接配る資料」ではなく、営業担当が商談シナリオを組み立てるために活用する“社内資産”である点にあります。
一般的な事例紹介資料が「成果をアピールするパンフレット」だとすれば、事例シートは営業が会話を動かすためのシナリオ台本のようなもの。
数字の成果だけでなく、背景やプロセス、意思決定のポイントまで記録することで、誰でも再現性を持って使えるのが強みです。
事例シート サンプル
案件名:製造業A社(従業員30名、年商20億円)
商談ステージ:比較検討フェーズ
1. 顧客課題(Before)
・案件管理が営業個人に属人化しており、進捗把握に時間がかかる
・営業会議の準備に毎週5時間以上を費やしていた
・顧客データが分散し、クロスセル提案がほとんどできていなかった
2. 提供した解決策
・案件進捗を共有できるSFAツールを導入
・営業会議用の定型レポートを自動生成
・商談ログをもとにクロスセル候補を抽出する仕組みを設計
3. 導入後の成果(After)
・営業会議の準備時間:5時間 → 1.5時間に短縮
・月次成約率が15%改善
・新規クロスセル提案が四半期で12件創出
4. 成果が生まれた背景・意思決定のプロセス
・経営層が「営業の仕組み化」を明確なテーマとして掲げていた
・初期は現場の抵抗もあったが、パイロット導入で成果を実感 → 全社展開に踏み切った
・成果の要因は「ツール導入」だけでなく、営業会議の進め方を変えたことが大きかった
5. 商談での活用ポイント
・比較検討フェーズで提示すると効果的
・「効率化」だけでなく「経営と現場の合意形成のプロセス」に話をつなげる
・「他社も最初は現場の抵抗があった」という文脈を紹介すると不安払拭につながる
なぜ今、事例シートが必要なのか
営業現場では、事例があっても以下のような課題が目立ちます。
- 商談で事例を活用できるのは一部のベテランだけ
- 成果の再現性がなく、新人や若手は経験不足のまま試行錯誤
- 知見が属人化し、組織に蓄積されない



結局、商談で事例を出せるかどうかは、個人の引き出し次第なんです。属人化してしまって、チーム全体に展開できないのが悩みです。



だからこそ“事例シート”が必要なんです。
単なる事例集ではなく、商談のプロセスごとに使える形に設計されたシート。
これがあれば、再現性を持って商談を前進させられるようになります。
つまり、事例シートは「顧客向けPR資料」ではなく、営業組織の武器庫です。
背景やプロセスを含めて体系的に整理することで、個人の経験をチーム全体の資産に変えられる。これこそが、事例シートが今の営業組織に不可欠な理由なのです。
事例活用の課題と現場での実情
多くの企業では「事例」を持っていても、それが営業現場で有効に活かされていません。
理由はシンプルで、情報が断片的かつ属人的になってしまっているからです。
社内で眠る“使われない事例集”
事例をまとめたスライドやPDFが社内共有フォルダに散在しているケースは少なくありません。
しかし「誰が、どの場面で、どう使うか」が明確になっていないため、結局は資料の存在すら知られていなかったり、営業担当が場当たり的にアレンジして使ってしまうのです。



事例を集めた資料はあるんです。
でも、営業メンバーが実際の商談でどう使えばいいかがイメージできない。結局“見せて終わり”になってしまってるんですよね。



よくある状況ですね。
事例集が“展示会のカタログ”のように並んでいるだけでは、商談の流れに組み込む設計ができていないんです。
成果だけを切り取った事例の落とし穴
もう一つの問題は、「成果だけを切り取った表面的な事例紹介」になりがちなことです。
定量成果(売上○%アップ、工数△時間削減など)は分かりやすいものの、そこに至るまでの背景やプロセスが抜け落ちると、顧客の共感や納得感は得られません。
結果として営業担当は「この事例をどう語ればいいか」迷い、属人化したトークスキルに頼らざるを得なくなります。
その結果、「使えない事例集」を量産する悪循環に陥ってしまうのです。
成功のためのポイント
- 事例を「社内利用用」と「顧客提示用」に分ける
- 社内版では背景・プロセス・意思決定の裏側まで詳細に残す
- 情報が新鮮なうちに関係者インタビューを実施する
- 可能であれば顧客側にも協力を依頼し、本音や懸念事項まで掘り下げる
実務のヒント
事例を“社内利用用”と“顧客提示用”に分けて設計することが重要です。
社内版では成果だけでなく、背景やプロセス、意思決定の裏側まで詳細に残すようにします。そのためには、情報が新鮮なうちに関係者へインタビューを行い、多面的な視点で整理することが効果的です。
手っ取り早いのは、社内の関係者を集めてプロジェクトの振り返りを実施すること。
ですが、本当に成果につなげたいならば、可能であれば商談相手にも協力を得て、社内でどんな議論や懸念があったのか、本音の部分に踏み込んで聞くことをおすすめします。
成功する事例シートの基本構成
事例シートを効果的に活用するためには、単なる「実績紹介」ではなく、商談を前進させるためのストーリー構成に整理することが重要です。
特にBtoBの商談では「課題 → 解決策 → 成果」の流れが鉄板型として機能します。これに背景や意思決定プロセスを加えることで、相手の共感や納得感を得やすくなります。
基本の3ステップ構成
- 課題(Before)
顧客が抱えていた具体的な問題を明示する。
例:営業会議に時間がかかる、見込み案件の進捗が見えない など。 - 解決策(Action)
どんな取り組みを実施したのかを整理する。
例:SFA導入、業務プロセス改善、マニュアル整備など。 - 成果(After)
定量・定性的な効果を提示する。
例:工数削減〇%、成約率△%改善、現場の不満解消など。
成功するシートの追加要素
- 成果の背景・プロセス
なぜ成果が出たのかを説明する文脈。導入に至る議論や意思決定を含めると説得力が増す。 - 意思決定の裏側
社内の抵抗や検討プロセスを盛り込むことで、相手が「自社でも起こりそうな壁」を想像できる。 - 商談での活用ポイント
どのステージで、どう提示すると効果的かを具体的に書き添える。
成功のためのポイント
- 課題 → 解決策 → 成果 の流れを守る
- 数字だけでなく背景・意思決定の文脈を必ず含める
- 商談プロセスごとに「どこで使うか」を設計する
- 顧客の懸念や抵抗をあえて書き込み、営業トークの材料にする
実務のヒント
商談プロセスごとに事例を切り分ける設計が有効です。
例えば、初回訪問では「共感型の事例」(同業他社の課題を共有)、比較検討フェーズでは「差別化型の事例」(競合との違いを示す)、導入直前には「安心型の事例」(導入時の懸念払拭)を提示するなど、シナリオと事例をひも付けることが成功のポイントになります。
商談を前進させるフォーマット設計の思想
事例シートの「型」自体はシンプルですが、成果を左右するのは フォーマット設計の思想 にあります。
重要なのは「誰に」「どの場面で」「どんな狙いで」使うかを想定した設計です。
設計の思想 ― “場面別に切り出せる”こと
このフォーマットの特徴は、事例を丸ごと見せる前提ではなく、小さな要素に分解して使える形にすることです。
営業の現場では、商談相手の関心やフェーズによって「使える切り口」は異なります。
- 初回訪問では「同業他社の課題」を示して共感を得る
- 比較検討フェーズでは「解決策と成果」で差別化を訴求
- 最終決定フェーズでは「意思決定の背景」を紹介し安心感を与える
つまり、フォーマットは「情報の倉庫」ではなく、営業が必要なピースを瞬時に取り出せる カード型の仕組み として設計します。
運用のポイント ― “営業トークとひも付ける”
シートは読む資料ではなく、会話を展開するための台本です。
営業担当が「顧客の質問や懸念に応じて切り出せる」状態にしてこそ効果を発揮します。
成功のためのチェックポイント
- 事例は“抜粋・切り出し”できる単位に整理する
- 商談フェーズごとに使える要素を明確化する
- 営業トーク例をシートに埋め込み、反論対応まで設計する
- 利用後のフィードバックを集め、フォーマットを継続的に改善する
運用の仕組み化と役割分担
事例シートは一度作って終わりではなく、継続的に更新・活用されてこそ価値が出る資産です。
そのためには「誰が情報を集め」「誰が編集し」「どう営業現場に届けるか」を明確にする必要があります。
情報収集と編集の分担
営業担当は素材を提供し、営業企画やマーケティング担当が編集を担う形が理想です。
営業が書くと「成果自慢」になりがちですが、編集側が顧客視点を加えることで、使いやすいシートに整えられます。
現場への展開と定着
せっかく作ったシートも現場に浸透しなければ意味がありません。
SFAや社内ポータルに格納して検索しやすくするほか、営業会議で活用事例を共有する仕掛けをつくると利用が広がります。
運用を仕組み化するポイント
- 営業は素材提供、編集担当がフォーマット化する分業体制にする
- SFAや社内ポータルで誰でもアクセスできるようにする
- 営業会議での共有をルーティン化し、活用を習慣にする
まとめとチェックリスト
事例シートは「顧客向けの事例紹介資料」ではなく、営業組織が商談を前進させるための社内資産です。
数値的なビフォーアフターだけでなく、背景や意思決定のプロセスまで含めて整理し、営業シナリオとひも付けて活用することで、属人化を防ぎ、再現性のある営業を実現できます。
また、作成そのものよりも 運用の仕組み化 が成果を分けます。
営業が素材を提供し、編集担当がフォーマット化する分業体制を取り、現場への展開と定着を図ることで、初めて組織的な武器になります。
チェックリスト
- 課題 → 解決策 → 成果 の流れで整理しているか
- 背景や意思決定プロセスも記録しているか
- 商談フェーズごとに活用ポイントを設計しているか
- 営業は素材提供、編集担当が整形する分業体制があるか
- SFAや営業会議を通じて現場に定着させているか
これらを押さえれば、事例シートは「ただの紹介資料」から脱却し、商談を前進させるための武器として機能します。
自社の仕組みに組み込むことで、チーム全体の営業力を底上げできるはずです。