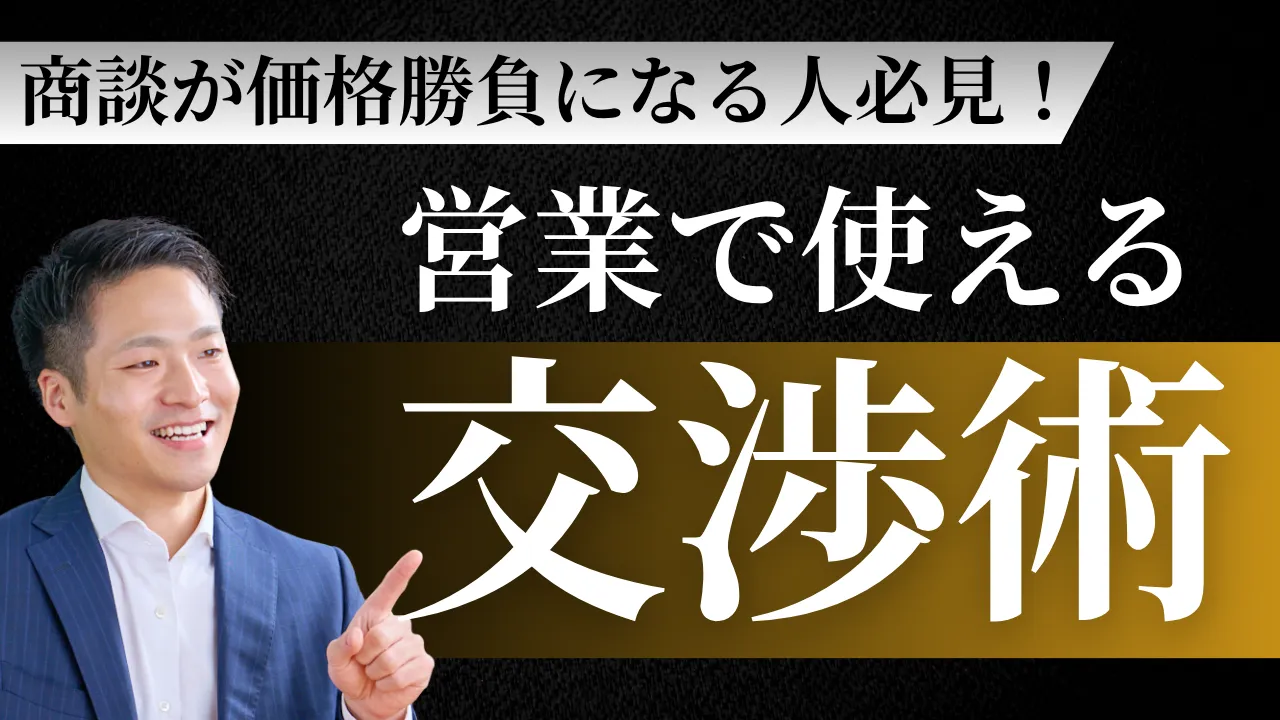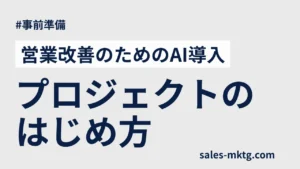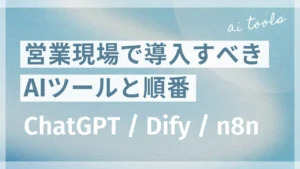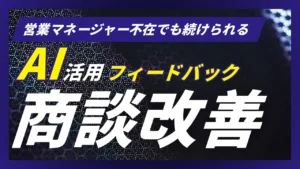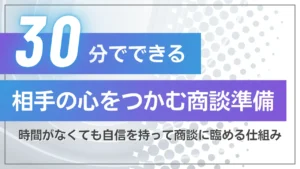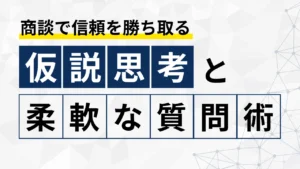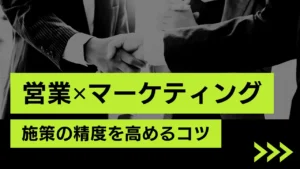初回商談のヒアリングで、相手が「まだ検討段階なんですよ」「他社さんとも話してて…」と言うと、その瞬間に少し身構えてしまう――そんな経験はありませんか。
「本気度が低いのでは?」と感じてしまい、つい自社の提案を急いで説明してしまう。
 営業マネージャー
営業マネージャーヒアリングのつもりが、結局こちらが話して終わっちゃうんですよね。相手の“本音”が見えないまま…。



実は、そこで大事なのが“交渉思考”なんです。交渉とは、駆け引きではなく“相手の選択肢を理解する思考”なのです。
ヒアリングを“情報収集”で終わらせず、“合意を設計する入口”に変える。これが、今の営業に求められている「交渉思考」です。
相手がどんな状況で、どんな選択肢を持ち、何を避けたいと思っているのか。
それを丁寧に引き出すことができれば、選ばれる提案が可能になります。
はじめに:営業にこそ“交渉思考”が必要な理由
営業という仕事は、長く「提案力」や「説明力」が重視されてきました。
しかし、提案が通るかどうかは“説明の上手さ”ではなく、相手との関係の中でどう合意をつくれるかにかかっています。
つまり、営業の本質は「交渉」――それも、駆け引きではなく“合意形成のデザイン”にあります。
提案が通らないのは「納得の構造」が欠けているから
BtoB商談では、担当者が納得しても決裁者が止める、条件の優先度が途中で変わるなど、相手企業の内部事情で合意が複雑化します。
営業側がどれだけ論理的に提案しても、相手の意思決定プロセスを理解していなければ合意は進みません。
ここに必要なのが交渉思考です。
交渉思考では、「相手がどんなBATNA(合意に至らない場合の最善策)を持っているか」を考えます。それを理解することで、相手が“何を譲れないのか”“何に安心したいのか”が見えてくる。
これがわかれば、提案を「押す」必要はなく、相手が自ら納得して決める状態をつくることができます。
「説得型営業」から「設計型営業」へ
従来の営業は、“説得して契約を取る”スタイルでした。
しかし今は、相手企業も複数の情報を比較し、条件を慎重に検討しています。この環境では、単に説得しても「他社を見てから決めます」で終わってしまう。
交渉思考を取り入れると、営業は相手の選択肢を把握しながら、自社が選ばれる理由を構造的に設計できるようになります。
「交渉=後半の駆け引き」ではなく、最初のヒアリングから始まる“合意の設計”として捉える。
これが、今の営業に求められる発想転換です。
例えば:提案が通らなかった商談での気づき
私自身、かつて提案に手応えを感じていたのに、最終段階で「社内の判断で見送りになりました」と言われたことがありました。
当時は「プレゼンの説得力が足りなかった」と思っていましたが、あとで冷静に振り返ると、相手の“別の選択肢”を聞き切れていなかったんです。
担当者は他部門との調整に苦労していて、「失敗できない」プレッシャーの中にいた。
その背景を理解せずに、自社の強みを一方的に話していた――。
その経験がきっかけで、私はBATNAの考え方を知り、「相手が何を選べる状態にあるのか」を整理してから提案するように変えました。
すると、不思議と値引き交渉が減り、商談の流れがスムーズになったのです。
営業が持つべき交渉思考
営業が交渉思考を持つというのは、「値引きせずに受注する」ためではありません。
むしろ、相手と自社の立場を整理し、どんな条件ならお互いが“納得して進める”のかを可視化する力です。
この視点を持つことで、ヒアリングから提案・交渉までが一本の線でつながり、商談の再現性が高まります。
営業に活かせる交渉術の基本:BATNAとZOPA
営業の現場では、「相手の反応を見ながら柔軟に対応する」という姿勢が大切にされてきました。
しかし、感覚頼りのやりとりだけでは、状況の変化に振り回されてしまいます。
ここで役に立つのが、交渉を“構造”として理解するためのフレーム――BATNA(バトナ)とZOPA(ゾーパ)です。
BATNAとは:「合意できない場合の最善策」
BATNA(Best Alternative to a Negotiated Agreement)は、「もしこの商談がまとまらなかった場合、次に取れる最善の選択肢は何か?」という視点です。
営業側で言えば、
・この提案が通らなかったら、他にどんな見込み案件があるか
・この条件で折り合わなければ、どこまでリソースを投入する価値があるか
を冷静に整理すること。
相手側で言えば、
・他社に依頼する
・内製化する
・そもそも発注を見送る
といった代替案の存在です。
この「お互いの最善策」を整理すると、無理に成立させなくていい商談が見えてきます。
実際、BATNAを持たずに交渉に入ると、焦りから値引きや譲歩をしてしまうケースが多い。
一方、自分のBATNAを把握していれば、どの条件で離脱すべきかを明確に判断できるのです。
ZOPAとは:「合意が成立する範囲(ゾーン)」
ZOPA(Zone of Possible Agreement)は、お互いのBATNAを踏まえた上で、合意が成立しうる条件の範囲を指します。
たとえば、相手の希望価格が90万円、自社の最低販売ラインが100万円だとします。
この間(90〜100万円)がZOPA。
しかし、金額だけでなく「納期」「支援範囲」「支払い条件」なども含め、交渉要素を広く設計すれば、ZOPAの幅を広げることができます。
ZOPAを把握できれば、「この条件なら合意できる」「ここを越えると無理」という判断軸が共有できるため、感情ではなく構造で交渉を進めることが可能になります。
営業現場での応用:BATNAとZOPAを“商談設計”に組み込む
商談前の準備段階で、次の2点を整理するだけでも、交渉の安定感が変わります。
- 自社のBATNAを明確にする
この商談が流れても「他にどう動くか」を具体的に想定しておく。
→ 焦って譲歩しないための心理的な支えになる。 - 相手のBATNAを仮説で立てておく
「相手は他社を検討している」「内製化を検討しているかも」など、仮説を立ててヒアリングで確認する。
→ 交渉が始まる前に、ZOPAの広がりを見極められる。
こうした準備をすることで、交渉は“即興の駆け引き”ではなく、「どんな条件なら合意できるかを整理する会話」に変わります。
営業が意識すべきポイント
BATNAとZOPAは、交渉の専門用語として知られていますが、実際には「商談の地図」を描くための実務ツールです。
この2つを整理するだけで、営業は感情的な“値引き交渉”から抜け出し、理性的に合意を設計する思考プロセスを持つことができます。
交渉思考で商談が変わる ― 営業が得る3つのメリット
BATNAやZOPAのような交渉理論を取り入れると、営業活動は「相手の反応を見て動く」から「合意を設計して動く」へと変化します。
この思考の切り替えによって、商談の手応え・スピード・再現性が大きく向上します。
ここでは、営業が交渉思考を取り入れることで得られる3つのメリットを整理します。
メリット1. 商談の“主導権”を取り戻せる
多くの営業が、商談の後半になると相手のペースに巻き込まれがちです。
「上司に相談します」「他社と比較してから決めます」――。この段階で主導権を失うのは、相手の選択肢(BATNA)を把握していないからです。
交渉思考を取り入れると、
・相手がどんな選択肢を持っているか
・その中で自社提案がどの位置にあるか
を冷静に整理できるため、会話の舵を自分で取れるようになります。
無理に押し切るのではなく、相手の枠組みの中で合意を設計することができる。結果、商談の流れがぶれにくくなります。
メリット2. ヒアリングが“情報収集”から“戦略設計”に変わる
交渉思考の最大の利点は、「聞き方」が変わることです。
従来のヒアリングは「ニーズを聞く」ことが目的でした。
しかし交渉思考では、“相手のBATNAを探る”ことが目的になります。
たとえば、
・「今回の検討では、どんな選択肢を見ておられますか?」
・「もし導入が難しい場合、他にどんな方法を考えられていますか?」
といった質問が、相手の本音や制約を引き出すきっかけになります。
こうした質問を重ねることで、相手の内部事情や優先度が見えてくる。
それが提案設計の材料となり、後半の価格交渉や条件調整がスムーズになるのです。
メリット3. 値引きではなく“納得”で合意できる
BATNA・ZOPAを意識して商談を設計すると、交渉の焦点が「価格」から「条件のすり合わせ」に変わります。
営業側が自社のBATNAを把握していれば、「ここまでなら譲れる」「この条件なら価値を保てる」という基準を持てます。
一方で、相手のBATNAを理解できれば、「なぜこの条件が必要なのか」を一緒に整理できる。
結果として、値引きではなく“納得ベースの合意”が生まれます。
価格を下げずに選ばれる理由をつくる――これこそ、交渉思考の本質的な成果です。
交渉思考が営業を“再現可能な仕事”に変える
営業の成果は属人的だと言われがちですが、交渉思考を取り入れることで、合意形成までのプロセスを「再現可能な構造」にできます。
相手の選択肢を理解し、自社のBATNAを整理し、ZOPAを見極める。
この3ステップを意識するだけで、商談は「運に頼らない」活動へと変わります。
実例:サイト制作商談で見えた“第三の選択肢”
中小企業A社とのサイト制作商談でのこと。
A社は経営の立て直し期にあり、初めて本格的にマーケティングに取り組もうとしていました。
比較検討していたのは、副業人材の活用、低価格の制作会社、そして私への依頼。
いずれの提案も「情報発信の仕組みを整える」という点では共通していましたが、A社の意思決定は“価格”と“安心感”の狭間で揺れていました。
相手のBATNAを整理する:選択肢はあるが決め手に欠ける
ヒアリングを重ねると、A社の他の選択肢には明確な制約が見えてきました。
- 副業人材への依頼:補助金が使えるが、開始は半年以上先。制作後のフォロー体制も不安。
- 低価格の制作会社:費用は安いが、マーケティングに詳しくなく、継続的な改善は難しい。
- 内製化:リソース・スキルの面で現実的ではない。
A社の担当・佐藤さんは根拠のない値引きを求めているわけではありませんでした。
「経営を立て直す時期だから、できるだけコストは抑えたい。
でも、マーケティングは初めてなので信頼できる人に任せたい。
制作後のことも考えると、副業人材は不安。」という現実的な判断軸を持っていたのです。
自社のBATNAと制約:強みは明確、でもフル対応は予算を超える
私は外部のパートナーと提携しており、マーケティング調査・設計・原稿作成・デザイン・コーディングまで一貫対応できる体制を整えています。
しかし、すべてをフルセットで対応しようとすると、A社の予算の約1.5倍になる見積もりでした。
私のBATNA(=この商談がまとまらない場合の最善策)は「他案件への注力」です。
知人経由での相談で、紹介案件であったのでなんとか対応したいという気持ちはありましたが、採算を度外視して値引きするより、しっかり利益を取れる案件を優先する方が合理的と考えていました。
ただ、A社との話の中で「フルセットではなくても、成果につながる形があるのでは」と感じていました。
ZOPAを見極める:本当に必要な価値は“内容”にあった
A社が望んでいたのは、SEOや広告流入を前提とした大型サイトではなく、「紹介や引き合いが多い中で、会社名検索時にきちんと情報を見せたい」という目的でした。
つまり、凝ったデザインよりも、事業内容を正確に伝える構成と信頼感のあるメッセージが重要。
ここに合意の余地――ZOPAが見えました。
“第三の選択肢”を設計する:テンプレート活用による簡易サイト制作
そこで提案したのが、値引きではなく「テンプレートを活用した簡易サイト制作」です。
- デザインは既存テンプレートを活用して工数を圧縮
- その分、原稿作成とメッセージ設計にしっかり時間を確保
- 更新は現場で難しいことを踏まえ、WordPressではなくより簡単なCMSでの運用
A社にとっては「すぐ始められて、長く安心して使える形」、自社にとっては「リソースを最適配分して採算を確保できる形」。双方が納得できる“第三の選択肢”が、ここで見つかりました。
交渉思考が導いた“納得の合意”
この商談を通じて実感したのは、BATNAとZOPAを意識すると交渉の重心が変わるということ。価格ではなく、価値の再設計によって合意を導ける。
交渉思考とは、相手の現実と自社の制約を整理し、“お互いに現実的で、前向きな合意を設計する力”なのです。
初回商談で意識すべきポイント ― 「相手の選択肢」を引き出す質問
初回商談は、交渉の「スタート地点」であり、ここでのヒアリング次第で商談の方向性がほぼ決まります。
しかし多くの営業は、「相手の課題」や「要望」を聞くことに意識が向き、満足してしまいます。
“相手がどんな選択肢を持っているか”を引き出すヒアリングまで実施することで、提案から受注の確率が高くなります。
「相手の選択肢」を聞く目的は“比較”ではなく“合意設計”
相手がどんな選択肢(BATNA)を考えているかを把握することは、競合を知るためではなく、「どうすれば相手にとって納得の合意になるか」を設計するためです。
たとえば、初回商談で以下のような質問をするだけでも、相手の考え方・不安・制約が見えてきます。
- 「今回の検討で、他にもお話しされている会社はありますか?」
- 「もし今回見送る場合、どんな進め方を考えておられますか?」
- 「今回のプロジェクトで“絶対に失敗できない点”はどこですか?」
これらの質問は、相手の選択肢を“整理する手伝い”でもあります。
相手自身が「どこまでを譲れるか」「何がリスクか」を言語化できると、商談の目的が共有されやすくなります。
「聞く順番」で信頼が変わる
質問そのものよりも大切なのは、“聞く順番”と“聞き方の温度”です。
いきなり「他社さんは?」と聞くと、警戒されるケースがあります。
まずは相手の背景・目的を確認し、自然な流れで選択肢を話題にするのがコツです。
- 目的・背景を確認する
「今回、どんなきっかけで検討を始められたのですか?」 - 理想像を共有する
「どんな状態になったら“うまくいった”と感じますか?」 - 選択肢を引き出す
「他にどんな方法や選択肢を考えられていますか?」
この順番を守るだけで、相手は“比較の質問”ではなく“理解の質問”として受け止めます。
相手の「BATNA」を聞き出したら、“不安”を一緒に言語化する
BATNAを把握できたら、次に意識したいのが「なぜそれを選びにくいのか」という不安の言語化です。
たとえば、
- 「副業人材を使うのは費用的に魅力だけど、進行管理が不安」
- 「低価格の会社は早いけど、品質が見えない」
といった発言が出れば、そこに“自社が補える余地(ZOPA)”が生まれます。
営業がこの不安を受け止めて整理してあげることで、相手は「この人は売り込みではなく、こちらの判断を助けてくれている」と感じます。
この段階で信頼が築かれれば、後半の交渉が驚くほどスムーズになります。
よくある誤り:「他の選択肢を否定して説得する」スタイル
ヒアリングの中で、他社や他の選択肢を聞いた際に、「そこはサポートが弱いですよ」「うちはその点が優れています」と、相手の選択肢を否定するような会話をしてしまうことがあります。
これは一見すると営業トークとして自然ですが、実は相手の心理的抵抗を強め、“防御モード”を生むリスクがあります。
交渉思考では、相手の選択肢を否定するのではなく、「なぜその選択肢に惹かれているのか」「どんな点に不安を感じているのか」を聞き出すことを重視します。
相手自身が選択肢の長所・短所を整理できるように導くことで、結果的に“自社を選ぶ理由”が相手の口から出てくるのです。
ヒアリングは“合意の入口”
初回商談の目的は情報収集ではありません。
「相手の選択肢を理解し、合意の土台をつくる」ことです。
交渉思考を持つ営業は、ヒアリングを通じて相手の構造を理解し、“売り込み”ではなく“共に整理する対話”で関係を築きます。
提案・検討フェーズでのZOPA思考 ― 合意を導く条件設計
商談の後半フェーズでは、提案書や見積もりをもとに「条件のすり合わせ」が始まります。
ここで営業が意識すべきは、“価格を下げるかどうか”ではなく、“どんな条件なら合意できるか”を整理することです。
この視点がZOPA思考です。
「合意できる範囲」を見える化する
ZOPA(Zone of Possible Agreement)とは、「お互いが受け入れられる条件の範囲」のこと。
交渉というと“値段交渉”のイメージが強いですが、ZOPAは金額以外の条件にも存在します。
- 納期を分ける
- 支払い条件を段階化する
- 提供範囲を一部調整する
- アフターサポートの内容を見直す
このような「条件の組み合わせ」を考えることで、単純な値引き交渉から脱却できます。
つまり、“どこで譲り、どこを守るか”の範囲を設計することが、ZOPAの実務的な使い方です。
価格調整ではなく、“条件設計”で合意を導く
多くの営業がつい陥るのは、「値引き要請=拒否か受諾か」の二択で考えること。
しかし実際には、「価格以外の変数」を動かすことで、双方が納得できる条件をつくれます。
- 納期を少し後ろ倒しにすることでコストを抑える
- 資料作成や確認作業を相手側に分担してもらう
- 成果物を段階的に納品することでリスクを分散する
こうした条件を再設計することで、「安くする」以外の道を提示できます。
交渉思考では、価格を動かす前に、ZOPAを広げる条件項目を洗い出すのがポイントです。
“相手の立場で”ZOPAを考える
ZOPAを設計するときに重要なのは、相手の評価基準を理解することです。
たとえば相手が「上司を説得しやすい根拠」を求めているなら、価格よりも「社内説明用の資料」を提案する方が効果的かもしれません。
また、経営者がリスクを嫌うタイプであれば、「トライアル期間」「中間レビュー」「返金保証」などの条件設計がZOPAを広げます。
営業側がZOPAを“自社都合”で考えると、相手には押し売りに見えます。
“相手の意思決定構造を支援する”という視点を持つことで、合意形成がぐっと早く、スムーズになります。
条件整理の実践ステップ
- 自社の譲れない条件を明確にする
最低ライン(価格・納期・範囲)を整理しておく。 - 相手の制約を把握する
予算・意思決定の構造・優先度などをヒアリング。 - 合意できる余地(ZOPA)を仮説立てする
価格以外の条件で広げられそうなポイントを検討。 - 複数案で提案する
「A案:標準プラン」「B案:分割実施」など、比較できる形で提示する。
この“複数提案”は、営業にとってのリスクを減らし、相手に「選べる安心感」を与えます。
これもZOPA思考の実践形です。
ZOPAは「条件交渉の地図」
ZOPAを意識した交渉とは、「譲歩の技術」ではなく「合意をデザインする技術」です。
どちらかが勝つ交渉ではなく、“お互いに納得できる合意点を構造的に見つける”ことが目的。
そのために、価格の前に条件を整理し、譲り方を設計する。
このZOPA思考こそが、値引きに頼らない商談を実現する鍵です。
BATNA思考で“合意を設計する営業”へ
本記事では、BATNAとZOPAという交渉理論をベースに、営業現場で「値引きせずに合意を導く」考え方を紹介しました。
これらの理論は単なるテクニックではなく、営業活動そのものを“再現可能なプロセス”に変えるための思考法です。
- BATNA:お互いの「代替案」を理解することで、焦らず商談を進められる
- ZOPA:お互いが納得できる「条件の範囲」を設計することで、価格以外の合意が生まれる
営業とは、「説得」ではなく「構造設計」です。
相手の選択肢を理解し、自社の立ち位置を冷静に整理できれば、値引きや感情論に流されず、双方にとって前向きな合意をつくることができます。
次の商談からは、「この相手のBATNAは何か?」「合意できるZOPAはどこか?」を意識してみてください。
それだけで、交渉の見え方がまったく変わるはずです。
“合意をデザインする営業”へ――それが、BATNA思考を持つ営業の第一歩です。