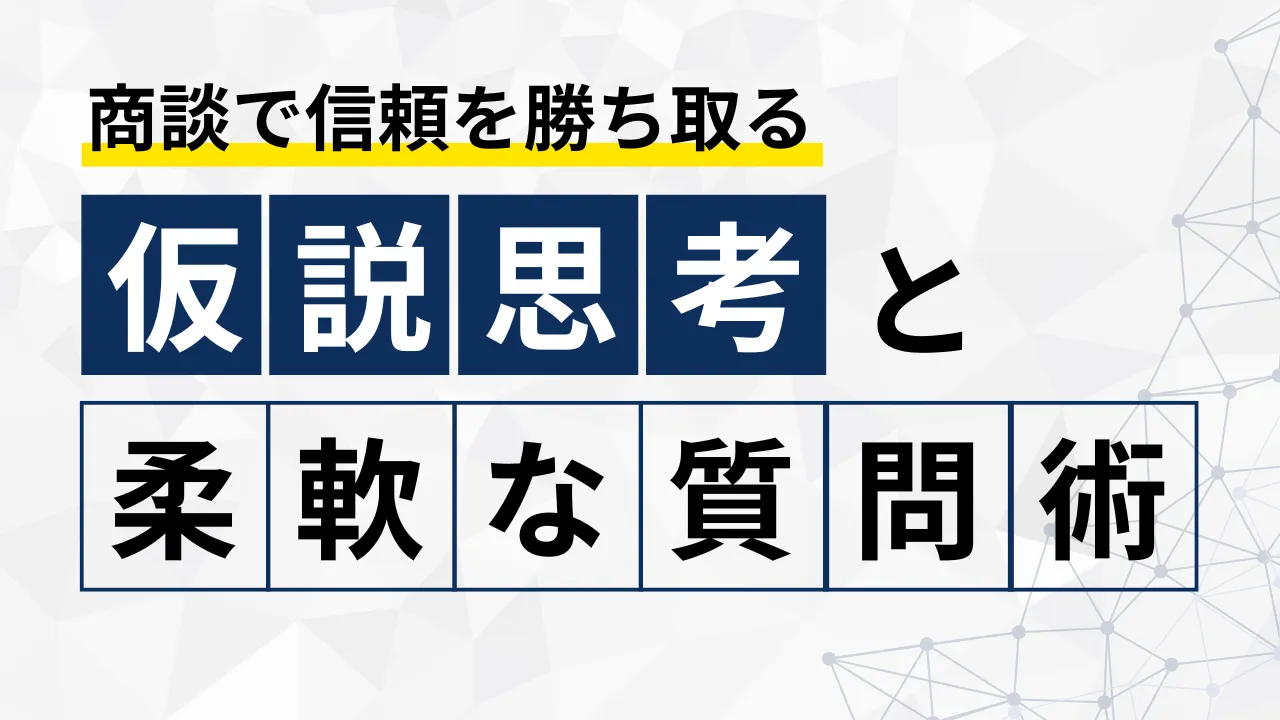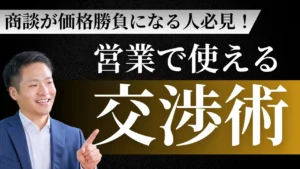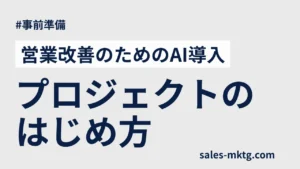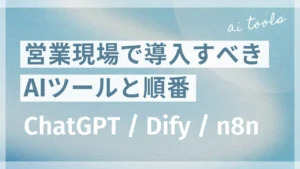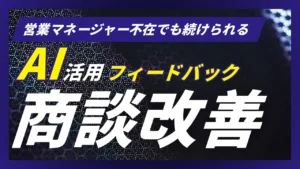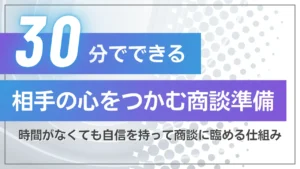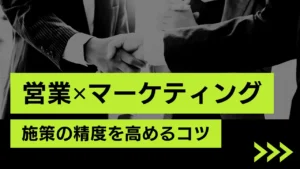初回商談で「信頼を勝ち取れるかどうか」は、その後の提案の通りやすさを大きく左右します。
信頼を得るための、営業担当は事前準備を行い、仮説を立てています。しかし、多くの営業は準備した仮説に固執してしまい、顧客の反応を見ながら柔軟にアップデートできていません。
本記事では、初回商談で信頼を得るための「仮説思考」と「質問術」を整理し、AI活用や実例を交えながら、再現性のある実践ステップを提示します。
初回商談。最初の数分間で「信頼できる相手かどうか」が決まってしまいます。
まず、相手の話を聞かずに、一方的に話し続ける営業を受け手は嫌います。これは、商談を受ける側を経験したことがある人なら誰でも共感することだと思います。
 営業マネージャー
営業マネージャー私のチームでも、仮説を立てて臨んではいるんですが、それを伝えることに必死になっているようです。
話がずれることを恐れて、準備してきたストーリーを押し通してしまうんです。



それはよくあるパターンですね。仮説を提示すること自体は悪くないのですが、固執すると“自分の話しかしない人”に見えて信頼を失ってしまうんです。
実際、初回商談でつまずく典型は「一方的な提案」や「事前準備にこだわりすぎて顧客の反応を無視する姿勢」です。これでは、せっかくの仮説思考も逆効果になってしまいます。
そこで重要なのが、仮説を早めに提示し、顧客の反応をもとに柔軟にアップデートしていく質問術です。これにより、顧客は「理解してくれている」「信頼できそうだ」と感じ、商談が前に進む土台ができます。
- 初回商談で信頼を失う典型パターンとその回避策
- 仮説を柔軟にアップデートするための質問の流れ
- AIを使った準備と現場での人の知見の使い分け
イントロダクション:初回商談で信頼を失う典型パターン
低額の商品やサービスではなく、複数回の商談が前提となる営業活動において、初回商談での最大の目的は「商品を売ること」ではなく、「信頼できる相手だ」と思ってもらうことです。
しかし、現場ではその目的を取り違え、信頼を損ねてしまうケースが少なくありません。
典型的な失敗パターンを整理すると、大きく3つあります。
よくある3つの失敗パターン
- 自社説明に偏りすぎる
自社の実績や商品説明に時間をかけすぎ、顧客の状況や課題を聞き出す時間がほとんどない。結果、「売り込み色」が強くなり、相手は身構えてしまいます。 - 仮説に固執する
事前に立てた仮説を崩すことに抵抗があり、顧客の反応をうまく受け止められない。たとえば「人材不足が課題ですよね?」と切り出して否定されたのに、そこから方向転換できずに話が空回りする。 - 会話のリズムを崩す
一方的に質問を連発して「尋問」のようになったり、逆に相手に話を任せすぎて主導権を失う。信頼構築に必要な「双方向性」がなくなります。
現場でよくある声



つい“最初の商談で形をつけなきゃ”と焦ってしまうんですよね…。結局、こちらが話しすぎてしまい、相手が何を考えていたのかよく分からないまま終わることもあります。



まさにそこで信頼を失ってしまうんです。顧客が求めているのは“商品説明”ではなく、“自分の話を理解しようとしてくれる姿勢”。ここを外すと、どれだけ良い提案でも届きません。
私自身の失敗体験
実は私自身も、同じ失敗を経験しました。コンサルティング会社に入社して初めての営業先は沖縄。
私は成功事例をまとめ、商圏分析も済ませ、その会社がその事業に参入できる可能性や自社からのサポート内容を熱心に伝えましたが、結果は惨敗。
振り返ると、自分が伝えることばかりに集中してしまい、相手から聞き出した情報はほとんどゼロでした。9割以上を一方的に話してしまったという苦い経験です。
信頼が次のチャンスをつくる
つまり、初回商談の落とし穴は「成果を急ぐあまり、信頼の土台づくりを飛ばしてしまうこと」です。
逆に言えば、信頼構築さえ意識すれば、十分勝負できるのです。なぜなら、信頼があれば「次回に改めて提案を聞いてみよう」という機会が生まれます。
しかし、信頼関係を築けなければ、そのチャンスすら与えられません。
仮説思考の正しい使い方 ― 固執せずアップデートする
仮説思考は商談準備の武器になりますが、「立てた仮説に固執してしまう」ことが最大の落とし穴です。本当に大切なのは、仮説を“会話の入口”として提示し、顧客の反応をもとに柔軟に修正していくことです。
仮説は「会話を開くカギ」
業界の一般的な課題を調べて提示すると、顧客は「そうではないんです、実は◯◯に困っていて」と補足してくれることが多いのです。つまり、仮説は当てることが目的ではなく、顧客から真の課題を引き出すきっかけなのです。
知ったかぶりせず、理解するスタンスを示す
相手もこちらが「業界のすべてを理解している」とは思っていません。大事なのは、知ったかぶりせず、理解しようとする姿勢を見せること。
「つまり◯◯について問題が大きいのですね」と整理して返すと、相手は「きちんと理解してくれている」と感じます。そのうえで、近い事例を提示すると「解決できそうだ」という信頼につながります。
聞くだけで終わらせない
若手営業がよく陥るのは「聞き出したけれど、解決の道筋を示せない」ケースです。
顧客は常に「結局、この人たちに解決できるのか」を見ています。したがって、ヒアリングとあわせて「自分たちがサポートできる可能性」を必ず示すことが必要です。
質問の広げ方と優先度の見極め
また、自社のサービス範囲が限られている場合、完全なオープンクエスチョンで広げすぎると収拾がつかなくなります。
最初は領域を絞って「他社ではこういう課題がありましたが、御社はいかがですか?」と聞き、もし優先度が低ければ「では、もっと大きな課題は他にあるのでしょうか」と広げる。この順番が効果的です。
なぜなら、顧客も社内リソースの制約を前提に考えています。
優先度の高い課題が放置されている限り、それ以下の問題解決は進まないからです。柔軟に仮説をアップデートしながら、最も優先すべき課題にたどり着くことこそ、信頼を勝ち取るポイントです。
信頼を勝ち取る質問術 ― 課題ヒアリングから解決力提示へ
初回商談では「どれだけ質問できるか」が重要ですが、単に質問を重ねるだけでは信頼は得られません。
顧客は「この人は自分たちの話を理解し、解決してくれるのか」を常に見ています。つまり、質問はゴールではなく、解決力を伝える手段なのです。
質問のステップ設計
効果的な質問の流れは大きく3段階に整理できます。
- 現状確認の質問
「現在の◯◯の状況はどうですか?」と基本情報を収集する。 - 課題特定の質問
「その状況で特に困っている点はどこですか?」と掘り下げる。 - 解決に向けた橋渡しの質問
「仮に◯◯が改善されたら、どんな効果が見込めそうですか?」と未来に目を向けさせる。
この流れを踏むことで、顧客自身も問題を整理しやすくなり、解決策の必要性を実感しやすくなります。
「解決できる相手」と思わせる問いかけ
単なる質問ではなく、自社の解決力を自然に伝える工夫が欠かせません。
たとえば、
- 「同業のA社では◯◯が課題でしたが、御社ではいかがですか?」
- 「仮にこのプロセスが効率化されたら、他の部門への影響は大きいですか?」
このように「事例+質問」や「未来イメージ+質問」を組み合わせることで、相手は「この人なら解決してくれそうだ」と感じやすくなります。
信頼を深める質問の工夫
質問を重ねる際に注意したいのは、尋問にならないことです。相手の答えを一度整理して返す「リフレーズ」を挟むと、会話のテンポが自然になります。
例:「つまり、◯◯のプロセスに負担が集中しているのですね」
こうした確認をしながら質問を展開することで、顧客は「理解してくれている」と感じ、心理的に安心します。
AIと人の役割分担 ― 仮説準備と事例知見の活用
近年、営業準備におけるAIの活用は急速に進んでいます。リサーチや仮説構築にAIを使うことで、短時間で情報を整理でき、初回商談の精度を高めやすくなっています。
しかし、現場での信頼獲得においては、AIと人間それぞれの役割を正しく分担することが欠かせません。
AIが得意な「仮説準備」
AIは、大量の情報を短時間で整理する力に優れています。業界の動向、競合の取り組み、公開資料からの課題抽出などはAIが最も得意とする領域です。
これにより、営業担当者は「仮説ゼロ」で商談に臨むリスクを減らすことができます。
人が果たす「信頼構築」
一方で、実際の商談ではAIが作った仮説をそのまま投げるだけでは不十分です。
顧客は「自分ごととして理解してくれているか」を敏感に感じ取ります。そのため、相手の反応を観察し、問い直し、適切な事例を差し込む柔軟さは人間にしかできない部分です。
事例は「背景とストーリー」が差をつける
日本のBtoB市場では「実績・証拠・安心感」が信頼のカギとされています。
AIは事例を収集・要約することはできますが、その背景や解決までのストーリーを語ることはできません。商談相手が一番興味を持つのは、この「なぜその課題が生まれ、どう乗り越えたか」という部分です。
自社に実際の事例がある場合は、その前後の経緯も含めて伝えることで、相手は「自分たちにも置き換えられる」と感じやすくなります。AIの情報は表面的になりがちだからこそ、人が語る“生きた事例”が信頼構築の差を生むのです。
私の経験から
ここまで、初回商談での信頼獲得に必要な仮説思考や質問術、AIとの役割分担について整理してきました。
では、なぜ私がこのテーマを語れるのか。その理由は、自ら営業で失敗を重ね、そこから学んだ経験にあります。
営業が苦手だった過去
私はもともと営業が得意ではありませんでした。
コンサルティング会社に入社した当初は、準備した資料を一方的に説明してしまい、相手の反応を引き出せない商談が続きました。沖縄での初商談で9割以上を自分が話し続け、何も聞き出せず、惨敗した経験は今でも忘れられません。
失敗から学んだ「聞く力」
その後、数多くの商談を経験する中で気づいたのは、顧客は説明を聞きたいのではなく、理解してくれる相手を求めているということでした。
そこから「仮説を提示して修正する」「質問で解決力を示す」スタイルへと切り替えた結果、提案の通りやすさが大きく変わったのです。
支援先での実践知
さらに独立後は、中小企業の営業組織を支援する立場となり、数多くの現場で同じ課題に直面しました。
特に若手営業は「準備したことを話すこと」に偏り、相手の本音を引き出せず苦戦するケースが多い。だからこそ、私自身の失敗経験を踏まえ、再現性のある指導方法として仕組み化してきました。
私だから伝えられること
こうした実体験と支援先での実践知があるからこそ、私は「初回商談での信頼獲得」について具体的に語れると考えています。
単なる理論やフレームワークではなく、自分が転んだ経験と、それをどう乗り越えたかを交えて伝えることで、読者の皆さんにもリアリティのある学びを届けられるのです。
まとめとチェックリスト
初回商談で信頼を勝ち取れるかどうかは、その後の提案活動の成否を大きく左右します。
ここまで見てきたように、重要なのは「仮説を持って臨むこと」と「固執せずに柔軟に修正すること」、そして「質問を通じて解決力を伝えること」です。
さらにAIを活用した準備と、人だからこそ語れる事例やストーリーを組み合わせることで、相手に安心感と期待感を持ってもらえる商談へとつながります。
明日から実践できるチェックリスト
- 初回商談の目的を「売ること」ではなく「信頼を得ること」と再確認する
- 事前に業界課題や類似事例をリサーチして仮説を準備する
- 商談では仮説を早めに提示し、否定されたら素直にアップデートする
- 相手の言葉を整理してリフレーズし、理解している姿勢を示す
- 「事例+質問」や「未来イメージ+質問」で解決力を伝える
- AIで調べた情報は下地に、自分の経験や事例を交えて差をつける
信頼関係さえ築ければ、「次のチャンス」が生まれます。
逆に信頼を得られなければ、提案の機会すら与えられません。だからこそ、初回商談では“信頼構築”を最優先に据えることを忘れないでください。


営業・マーケティングの専門家が回答します。
まずはお気軽にご相談ください。